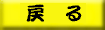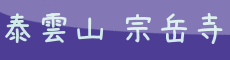
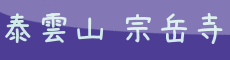
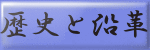
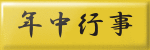
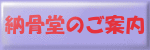
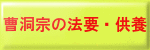
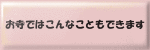
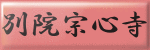
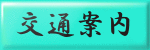
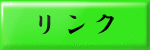
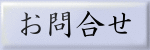
|
沿革
| ■山号 | 泰雲山(たいうんざん) |
| ■寺号 | 宗岳寺(そうがくじ) |
| ■宗派 | 曹洞宗(そうとうしゅう) |
| ■御本尊 | 釈迦如来(しゃかにょらい) |
| ■由緒 |
|
創建由緒は未詳の部分が多いが、はじめは天台宗の寺で「妙心寺」と号したと
いわれている。天正19(1591)年、肥前長崎より玄雪栄頓大和尚を請して中興開山とした。
その際に最も功績のあったのが加藤清正公の一族、田寺久太夫であり、「開基」
とされている。久太夫の法号「泰雲宗岳大禅定門」から「泰雲山宗岳寺」と称する
ようになった。清正公の築城以来、当寺が城の北東の方角、表鬼門に当たること
から、城の鎮護寺とされてきた。 本寺は長門国大寧寺で、末寺は熊本城下の宗心寺、阿蘇の極楽寺など5カ寺ある。 妙解院(細川忠利公)が入国以来代々お位牌を安置し、朝暮に御回向がなされてき た。しかし、本尊釈迦如来、木佛地蔵、毘沙門天、薬師如来、開山木像ほか諸仏像、 ならびに霊感院(細川重賢公)筆の額、客殿、茶室、庫院、宝蔵、衆寮、鐘楼門、 鎮守堂などが、再三の戦火によって失した。また、明治10(1877)年の西南の役によって伽 藍は灰燼に帰した。 現在の本尊釈迦三尊像(釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩)は、細川家の菩提寺で あった立田山泰勝寺(臨済宗。明治時代に廃寺)より迎えられ、ほかに達磨大師像、 道元禅師像、鎌倉時代の彫刻家運慶作といわれる毘沙門天像などがまつられている。 また、殿鐘は、もとは川尻大慈寺(曹洞宗、大本山永平寺末)の所蔵で、応永16 (1409)年足利義満時代の鋳造である。墓地には、松野家、三渕家、稲津家、堀家 など細川家重臣や、幕末の藩医で明治初期に熊本医学校創設に尽力した寺倉秋堤、 関口流抜刀術の師範で国学者、歴史家でもあった井澤蟠龍など著名な数多くの墳墓があり、明治期には文豪 森鴎外も参詣したという記録も残っている。 |
 井澤蟠龍の墓 |  歴代住職の御廟 |
| 当寺開山 | 玄雪栄頓大和尚 | 寛永10(1633)年1月7日遷化。 | 当寺開基・田寺久太夫から拝請され、肥前長崎より来住。 |
| 二世 | 寒雄壽泉大和尚 | 寛文5(1665)年6月7日遷化。 | |
| 三世 | 斧山藝 大和尚 大和尚 |
寛文6(1666)年12月20日遷化。 | |
| 四世 | 石田玄春大和尚 | 万治3(1660)年7月16日遷化。 | 熊本市坪井・宗心寺の開山とされる。 |
| 五世 | 法水梁遠大和尚 | 元禄9(1696)年9月10日遷化。 | |
| 六世 | 庭嵓普門大和尚 | 正徳元(1711)年7月21日遷化。 | |
| 七世 | 單州不傳大和尚 | 元文4(1739)年9月4日遷化。 | |
| 八世 | 損道法益大和尚 | 宝暦9(1759)年10月13日遷化。 | |
| 九世 | 白室一明大和尚 | 安永3(1774)年2月15日遷化。 | |
| 十世 | 真 洞龍大和尚 洞龍大和尚 |
寛政12(1800)年9月8日遷化。 | |
| 十一世 | 奇巌法泉大和尚 | 文政13(1830)年11月2日遷化。 | |
| 十二世 | 廓山天然大和尚 | 天保2(1831)年2月9日遷化。 | |
| 十三世 | 天山恵日大和尚 | 天保14(1843)年2月9日遷化。 | |
| 十四世 | 法山真瑞大和尚 | 明治4(1871)年12月21日遷化。 | |
| 十五世 | 金縄轉牛大和尚 | 元治元(1864)年4月29日遷化。 | |
| 十六世 | 琢峯痴温大和尚 | 明治12(1879)年11月6日遷化。 | |
| 十七世 | 透雲龍道大和尚 | 明治40(1907)年7月28日遷化。 | 明治10年の役で焼失した伽藍を復興し「中興」とされる。 |
| 十八世 | 晩成龍華大和尚 | 昭和9(1934)年5月15日遷化。 | |
| 十九世 | 静雲無着大和尚 | 昭和40(1965)年9月28日遷化。 | |
| 二十世 | 大心和昭大和尚 | 平成19(2007)年3月30日遷化。 | 伽藍の復興や檀信徒会館の建築に尽力。 |
| 二十一世(現住) | 能海雪心大和尚 | まだ娑婆(しゃば)世界におります。 | |